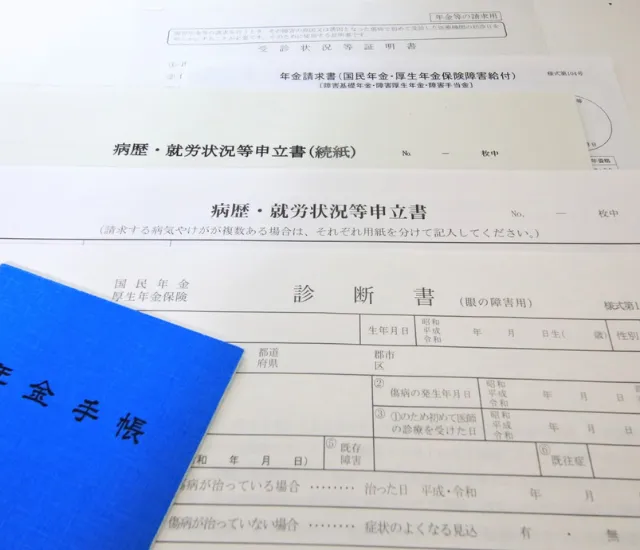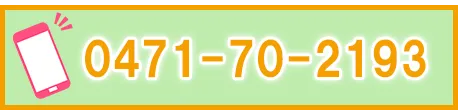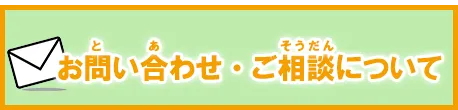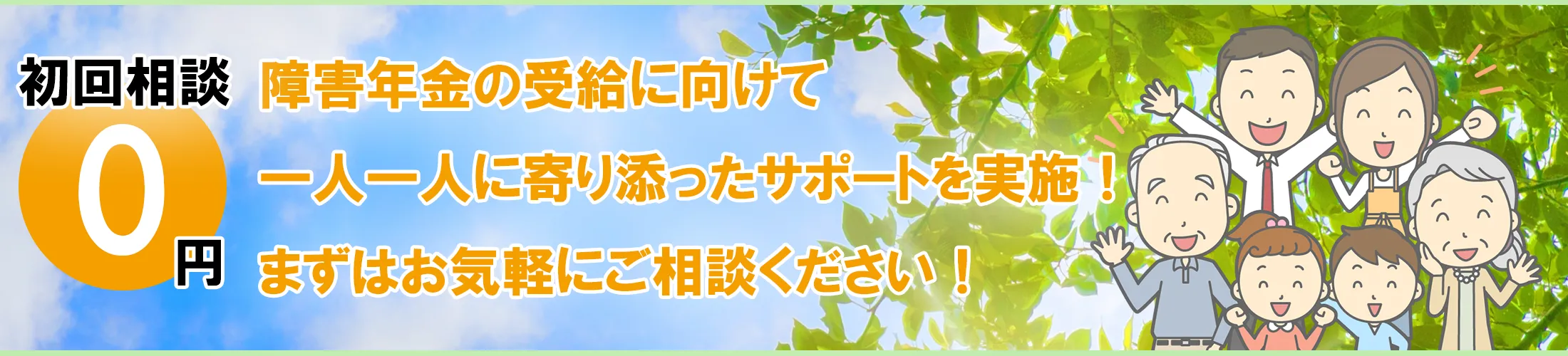高次脳機能障害は外見からは分かりにくい障害ですが、日常生活や仕事に大きな影響を及ぼします。
しかし、障害年金の認定基準は複雑で、診断書の書き方や生活状況の証明が不十分だと、不支給になってしまうケースも少なくありません。
この記事では、高次脳機能障害と診断された方やそのご家族に向けて、障害年金の認定基準、必要な書類、申請の流れなどについて解説します。
高次脳機能障害で今後の生活に少しでも不安や疑問がある方は、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
必ず認定が下りるわけではありませんが、ご相談者様の状況に合わせ、最適な申請方法をご提案し、最大限サポートいたします。
高次脳機能障害とは?
高次脳機能障害とは、記憶・注意・遂行機能・社会的行動といった高度な脳の働きに障害が生じる状態のことです。
外見からは分かりにくいため周囲に理解されにくい特徴があり、社会復帰や就労に大きな影響を及ぼします。

2025年時点で高次脳機能障害は障害年金の対象疾患として扱われていますが、診断されたから必ず受給できるわけでなく、診断・立証の仕方によって認定の可否が左右されます。
高次脳機能障害の原因
高次脳機能障害の主な原因は、主に次のとおりです。
- 脳梗塞や脳出血といった脳血管障害
- 交通事故などによる頭部外傷
- 脳炎
- 低酸素脳症
- 脳腫瘍など
これらはいずれも脳に損傷を与える要因であり、その結果、記憶や注意、遂行機能などの障害が現れます。
高次脳機能の代表的な症状
高次脳機能障害の代表的な症状は主に次のとおりです。
- 新しい出来事を覚えられない「記憶障害」
- 集中力が続かないといった形で日常生活に影響を与える「注意障害」
- 段取りや計画立案が難しくなる「遂行機能障害」
- 感情のコントロールが困難となり対人関係のトラブルを引き起こしやすくなる「社会的行動障害」
- 失語や理解・表現に障害が出る「言語障害」

他にもさまざまな症状がありますが、発現する症状や重症度には個人差があります。
障害年金における高次脳機能障害の認定基準
高次脳機能障害の認定基準は、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」の「第8節 精神の障害」で定められています。
大まかな認定項目は次のとおりです。
障害の程度 障害の状態 1級 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの 2級 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの 3級 1 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
2 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの障害手当金 認知障害のため、労働が制限を受けるもの
日常生活能力の評価
障害年金における高次脳機能障害の認定では、診断書に「日常生活能力の判定」が記載されます。
これは食事、着替え、入浴、金銭管理、対人関係といった生活行為を基準に、一人暮らしを想定してどの程度自立しておこなえるかを示す項目です。
7項目あり、これら項目を「できる」~「助言や指導をしてもできない若しくは行わない」の4指標で評価していきます。
日常生活能力の程度
日常生活能力の程度とは、生活の自立度つまり、日常の生活の能力を「ほとんどできず常時援助が必要」から「自立して行える」の5項目で評価する欄です。
日常生活能力の程度は、日常生活能力の評価と同様、高次脳機能障害用の診断書に記載欄が設けられています。
なお、これら2つの評価は、障害年金の受給可否、および受給等級に大きく影響するため、非常に重要な項目です。
労働能力の評価
就労しているからといって、障害年金の受給が不可になるわけではありません。
労働にどれだけ支障が出ているか、職場での支援や配慮が必要かどうかで評価され、支援が必要な状態であれば障害年金の認定対象です。
例えば、配置転換や短時間勤務を余儀なくされる、体調不良が続き中々出金できないという場合は労働能力の低下が認められ、障害年金の対象となる可能性が高まります。
考慮される他のポイント
障害年金の等級評価は、日常生活能力の評価や、日常生活能力の判定、就労状況(就労している場合)だけではありません。
他に考慮されるポイントは次のとおりです。
- 現在の症状・状態
- 通院・服薬などの療養状況
- 家族の援助・福祉サービスの有無などの生活環境
これらの補足資料を揃えられれば、認定の可能性を高められます。
高次脳機能障害の障害年金申請時に必要な書類一覧
申請に必要な書類は主に次のとおりです。
- 受診状況等証明書
- 医師の診断書(障害年金用様式)
- 病歴・就労状況等申立書
ただし、上記はあくまでも代表的なものです。
年金手帳や所得証明書など、申請者本人の状況によって準備書類は異なります。

また、高次脳機能障害の症状によっては、別のタイプの診断書を用意しなければならないため、特に注意が必要です。
高次脳機能障害の障害年金認定における課題・注意点
高次脳機能障害は外見上わかりにくいため、診断書や生活記録が不十分だと不支給になるケースが多いです。
不支給になるケースでは、診断書に具体的な症状が記載されていない、日常生活報告が抽象的すぎるなどの共通点が確認されています。
これを防ぐためには、医師に症状を的確に記載してもらうこと、家族が詳細な生活記録を残すことが重要です。
高次脳機能障害の障害年金申請でお悩みの方へ
- 障害年金を申請したいが、手続きが複雑で何からはじめればよいか分からない
- 初診日の証明や書類集めに苦労している
- 申請が通るか不安、過去に不支給になった経験がある
- 仕事や治療で忙しく、申請に十分な時間を割けない
こうしたお悩みをサポートするため、障害年金申請に精通した社会保険労務士が、初回相談から受給まで一貫してお手伝いしています。
申請代行サービスを利用するデメリット
申請代行を依頼する場合、下記のようなデメリットがあります。
- 着手金や事務手数料などの初期費用がかかる(初期費用は申請が不支給となった場合でも返金されないことが一般的)
- 依頼する社労士によって対応の質や業務範囲が異なる
- 手続きの詳細を把握しづらくなるため、手続きの流れを把握したい方には不向き
- 自分でできる部分が多い場合、費用に対して得られるメリットが少ない場合がある
申請代行サービスを利用するメリット
一方、申請代行サービスを利用するメリットは次のとおりです。
- 成果報酬型のため、受給が決定するまで報酬を支払いする心配がありません
- 個人申請よりも高い認定率で、安心して任せられます
- 申請後のアフターフォローや更新サポートも充実
- 書類不備や手続きミスによる不支給リスクを大幅に軽減
- 外出困難な方には出張相談も対応(条件あり)
鳥海社会保険労務士事務所が解決します
障害年金申請に特化した社会保険労務士が、初回無料相談から受給まで一貫してサポートいたします。
- 必要書類リストや記入例を提供し、書類作成・取得もフルサポート
- 初診日の特定や病院への確認も代行し、面倒な手続きはすべてお任せください。
- 受給可能性を事前に診断し、成功率の高い申請戦略をご提案
まずは無料相談をご利用ください
障害年金は初回の申請が最も重要です。「少しでも不安がある」「確実に受給したい」とお考えの方は、ぜひ鳥海社会保険労務士事務所の無料相談をご利用ください。
専門家があなたの状況を丁寧にヒアリングし、最適なサポートプランをご提案します。
お電話・問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。あなたの障害年金受給を全力でサポートいたします。

お電話の際は「障害年金のホームページをみた」とお伝えいただくと、ご案内がスムーズです。
まとめ
高次脳機能障害と向き合うと「仕事を続けられるのか」「家族に迷惑をかけてしまうのでは」と不安を感じる方は多いはずです。
障害年金を活用すれば、経済的不安を軽減しながら、無理のない範囲で生活を送れます。
今回のポイントは主に次のとおりです。
- 高次脳機能障害の認定では「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」に基づき判断される
- 外見から分かりにくいため、心理検査や生活記録をしっかり揃え、主治医に伝えておくひつようがある
- 障害年金の申請には医師の診断書や初診日証明、日常生活状況報告書などの専門的な書類が必要なもの、準備すべき書類は申請者の状況によって異なる
「自分も対象になるのか不安」「手続きが複雑で難しい」と感じたら、まずは専門家へ早めに相談し、ご自身に合った最適な支援を受けることをおすすめします。