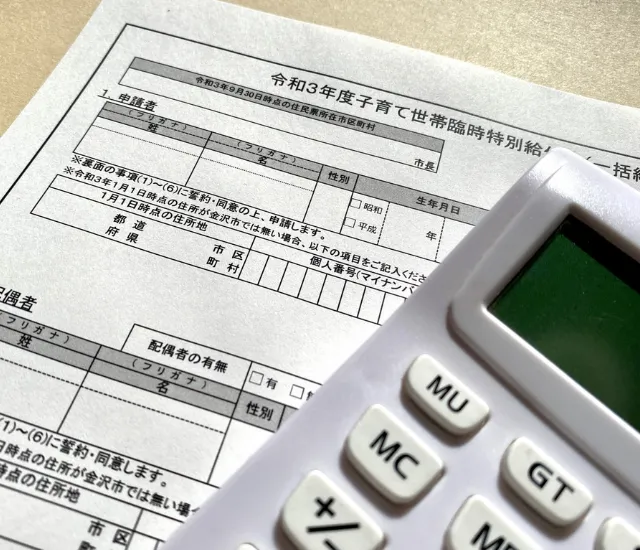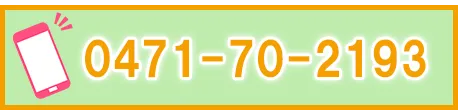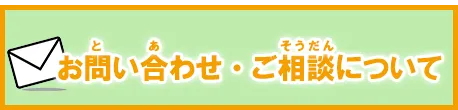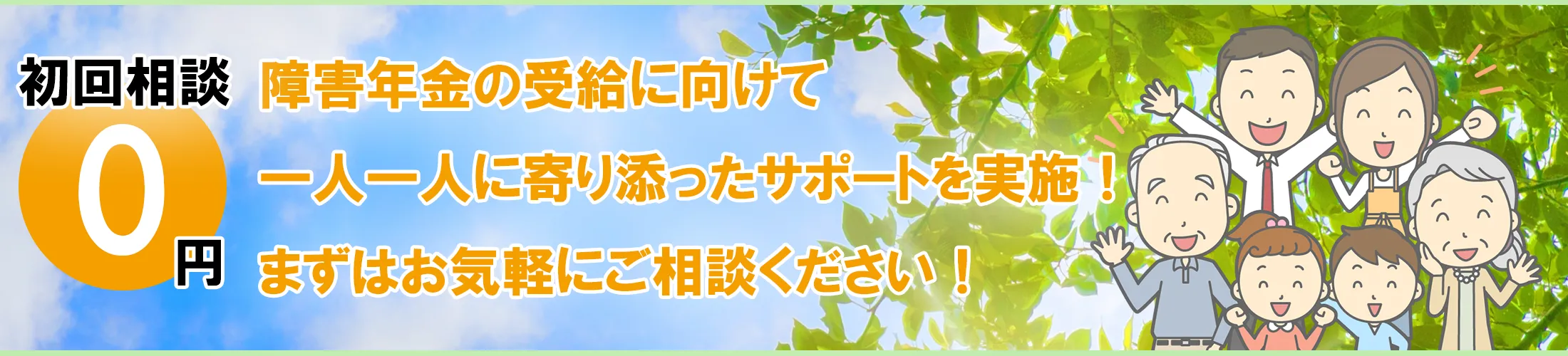うつ病と診断されたからといって仕事を辞める必要はありません。
しかし、うつ病の治療に専念するため、休職や退職する方は多く、それにともない収入の減少や、生活費や医療費のやりくりが難しいケースも少なくありません。
うつ病で働けなくなった場合、公的な支援金や補助制度を利用することで、経済的な不安を軽減しながら治療に専念できます。
この記事では、うつ病で仕事を休職・退職した方や、経済的な支援を必要としている方に向けて、うつ病で利用できる主な支援金や公的制度、申請のポイントについてわかりやすく解説します。

うつ病で働けなくなった場合、公的な支援金や補助制度を利用することで、経済的な不安を軽減しながら治療に専念できます。
この記事では、うつ病で仕事を休職・退職した方や、経済的な支援を必要としている方に向けて、うつ病で利用できる主な支援金や公的制度、申請のポイントについてわかりやすく解説します。
うつ病の方に活用をおすすめする支援制度
うつ病で働けなくなったり、生活や治療に不安を感じたりしている方のために、国や自治体が用意しているさまざまな支援制度があります。
ここでは、うつ病の方が利用できる代表的な公的支援金や制度について紹介します。
障害年金
障害年金とは、うつ病などの病気やケガによって日常生活や就労が著しく制限される際に受給できる公的年金です。
「初診日の特定」「保険料納付要件」「障害の状態」の受給要件を満たしていれば、現役世代問わず受給できます。
障害年金はうつ病の経済的な支えとなるため、受給できれば治療や生活の安定に大きく寄与します。
傷病手当金
傷病手当金は、うつ病などで会社員や公務員が休職した場合に、健康保険から一定期間生活費を補助する制度です。
標準報酬月額の2/3が最長1年6ヶ月支給されます。
申請には医師の診断書と事業主の証明が必要ですが受給できれば、急な収入減による経済的負担を軽減しながら治療に専念できます。
失業給付
失業給付は、うつ病などで離職した場合に雇用保険から生活費を支援する制度です。
通常、受給期間は離職日翌日の1年間ですが、受給期間中に病気療養などで働けない状態が30日以上続いている場合、受給期間の延長申請できます。(最長離職日翌日の4年以内まで延長可能)
生活保護
生活保護は、資産や収入が最低生活費を下回る場合に、医療費や生活費を全額保障する最後のセーフティネットです。
単身世帯で月額約13万円(地域差あり)が支給され、医療扶助によりうつ病の治療費も全額助成されます。
特別障害者手当
特別障害者手当は、常時介護が必要な重度障害者に対して支給される制度です。
月額2万9,590円(2025年度)が支給され、精神障害者保健福祉手帳1級を持っている方が対象となります。
なお、所得制限があり、受給所得者および扶養義務者の前年所得が一定額以上ある場合、支給されないため、事前に確認しましょう。
特別障害者給付金制度
特別障害者給付金制度は、国民年金の未加入期間により、受給要件を満たせず、障害年金を受給できない障害者を対象とした救済制度です。
月額5万円程度が支給されますが、支給対象が厳格に定められているため、自身が対象かどうかしっかりと確認する必要があります。
障害者手帳
障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)は、障害のある方がさまざまな支援や優遇措置を受けられる制度です。
所得税控除や交通料金割引、公共料金の減免などさまざまなサービスが受けられます。
自立支援医療
自立支援医療は、通院医療費の自己負担を1割に軽減する制度です。
精神科や心療内科の受診が対象となります。
通常自己負担は3割ですが、自立支援医療の活用により、負担額を1割に軽減できれば、治療費の負担を軽減できるため、継続的な治療を無理なく続けられます。
重度心身障害者医療費助成制度
重度心身障害者医療費助成制度は、健康保険が適用された医療費の自己負担の1部を助成する制度です。
所得制限や支給対象者が定められていますが、支給対象者で制度が活用できれば、治療費の自己負担額を抑えられるため、経済的な負担を軽減できます。
うつ病で障害年金などの支援金を活用するデメリット
支援制度を活用する際には以下の点に注意が必要です。
- 障害年金を受給して年収が一定額を超えると、健康保険の扶養から外れる場合があります。
- 自立支援医療は年1回、障害年金は1~5年ごとの有期認定で更新手続きが必要です。
- 書類の準備や申請手続きがストレスとなり、症状が悪化するケースもあります。
- 一部の制度では、将来の年金額や他の給付金に影響する場合もあります。

ただし、専門家のサポートを利用すれば、これらのデメリットを最小限に抑えられます。
不安や疑問がある場合は、早めに専門家へ相談しましょう。
うつ病で障害年金などの支援制度を活用しないリスク
デメリットはありますが、うつ病で支援制度を活用しないと次のようリスクがあります。
- 収入減で生活が困窮する
- 医療費や生活費の自己負担が増える
- 治療や療養に専念できず、症状悪化の可能性
- 家族や周囲への経済的・精神的負担が増える

経済的な負担を少しでも減らすためにも、これら支援制度の積極的な活用をおすすめします。
うつ病の障害年金申請でお悩みの方へ
- うつ病などで障害年金を申請したいが、手続きが複雑で何からはじめればよいか分からない
- 初診日の証明や書類集めに苦労している
- 申請が通るか不安、過去に不支給になった経験がある
- 仕事や治療で忙しく、申請に十分な時間を割けない
こうしたお悩みをサポートするため、障害年金申請に精通した社会保険労務士が、初回相談から受給まで一貫してお手伝いしています。
申請代行サービスを利用するデメリット
申請代行を依頼する場合、下記のようなデメリットがあります。
- 着手金や事務手数料などの初期費用がかかる(初期費用は申請が不支給となった場合でも返金されないことが一般的)
- 依頼する社労士によって対応の質や業務範囲が異なる
- 手続きの詳細を把握しづらくなるため、手続きの流れを把握したい方には不向き
- 自分でできる部分が多い場合、費用に対して得られるメリットが少ない場合がある
申請代行サービスを利用するメリット
一方、申請代行サービスを利用するメリットは次のとおりです。
- 成果報酬型のため、受給が決定するまで報酬を支払いする心配がありません
- 個人申請よりも高い認定率で、安心して任せられます
- 申請後のアフターフォローや更新サポートも充実
- 書類不備や手続きミスによる不支給リスクを大幅に軽減
- 外出困難な方には出張相談も対応(条件あり)
鳥海社会保険労務士事務所が解決します
障害年金申請に特化した社会保険労務士が、初回無料相談から受給まで一貫してサポートいたします。
- 必要書類リストや記入例を提供し、書類作成・取得もフルサポート
- 初診日の特定や病院への確認も代行し、面倒な手続きはすべてお任せください。
- 受給可能性を事前に診断し、成功率の高い申請戦略をご提案
まずは無料相談をご利用ください
障害年金は初回の申請が最も重要です。「少しでも不安がある」「確実に受給したい」とお考えの方は、ぜひ鳥海社会保険労務士事務所の無料相談をご利用ください。
専門家があなたの状況を丁寧にヒアリングし、最適なサポートプランをご提案します。
お電話・問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。あなたの障害年金受給を全力でサポートいたします。

お電話の際は「障害年金のホームページをみた」とお伝えいただくと、ご案内がスムーズです。
「うつ病 障害年金」でよくある質問
障害年金でよくある質問をまとめました。
もっとよく知りたいという方はぜひ参考にしてください。
1.フリーランスでも障害年金を受給できる可能性はありますか?
国民年金加入中に初診日があれば受給可能です。
フリーランスや自営業の方も、諦めずに申請を検討してください。
初診日証明と障害状態の立証が要件となり、専門家のサポートを受けることで申請成功率も向上しています。
2.申請却下後に再申請は可能ですか?
前回の申請内容との矛盾に注意しつつ、新たな医療証拠を追加すれば再申請が可能です。
ただし、初回申請と比べて、再申請は申請のハードルが高まるため、受給確率を少しでも高めたいのであれば、専門家への相談・依頼をおすすめします。
3.自力で障害年金の受給は可能ですか?
自分で申請することも可能です。
ただし、素人が申請すると、診断書の症状記載漏れや初診日証明の不備などにより、申請が却下されるケースが少なくありません。
社労士を利用した場合の受給率が高い傾向にあるため、不安がある場合は専門家のサポートを活用しましょう。
-

障害年金の申請を自力で行うことは可能?自力で可能な場合と社労士に依頼した方がよい場合も解説!
障害年金の申請を自力で行うことは可能です。しかし、障害年金の申請は専門性が高いため、知識がない方がイチから申請しようとすると手間や労力がかかる他、受給確率が下がるリスクがあります。当記事では自力申請が難しい理由や自力申請した方がよい場合などについてみていきます。
まとめ
うつ病で働けなくなった方は、公的支援制度や各種サポートを活用することで、治療と生活の両立が可能です。
経済的な負担が少ない生活設計を立てるためにも、これらの支援制度を積極的に活用することをおすすめします。
今回のポイントは主に次のとおりです。
- うつ病による収入減や生活困難には、傷病手当金や障害年金、自立支援医療などの制度が活用できる
- 障害年金の申請には初診日証明や診断書など、専門的な書類が必要
- うつ病で障害年金などの支援制度を活用する場合、デメリットがあることも理解しておく
経済的な負担がうつ病の回復を遅らせるリスクがあるため、困ったときは早めに専門家へ相談し、ご自身に合った最適な支援を受けることをおすすめします。